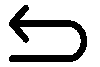004 愛媛県 白石の鼻巨石群の三つ石

【Introduction of Iwakura 4】Visit・Photo:2013.9.22 /Original:2014.2.16 / Write:2021.9.11

□分類:天文利用のための岩石遺構(広義のイワクラ)
□信仰状況:祭祀されていない、 白石龍神社との関係は不明
□岩石の形状:巨岩組
□備考:人工物、岩石遺構と太陽の関係の分類 スリットB-3型、周辺に岩石群

□住所:愛媛県松山市勝岡町
□緯度経度:33°54'25.3"N 132°42'32.1"E
(googleに入力すれば場所が表示されます)
愛媛県松山市の北端に白石の鼻という岬があり、海の中に三つ石と呼ばれる巨岩組があります。2008年に篠澤邦彦氏によって、この三つ石に春分・秋分の太陽が入る現象が発見されました。その後、篠澤邦彦氏は白石の鼻巨石群調査委員会を設立して、白石の鼻周辺の岩石の調査を継続されています。
三つ石は複雑に組上げられた巨岩組でそのスリット部分に、春分と秋分の日の日の入りの太陽の光が入ります。
ここで、スリットと呼んでいるのは、三つ石の逆三角形の穴の部分ではなく、その左上の細い隙間です。このスリット通して太陽が見えるのですが、これがいかに計算されつくした事なのかを理解してもらうには少し説明が必要です。
遠くの光源と観測者の間に穴を開けた画用紙を置き、観測者が画用紙の穴を通して光源を見るのは簡単です。しかし、この画用紙を筒に変えた場合、観測者がその穴から光源を見るのは難しくなります。画用紙の筒と光源を平行にし、そのライン上に観測者が立たないと見えません。三つ石のスリットの幅は狭く、岩の厚みは数メートルあるので、幅と厚みの比は大きいので、視野角は非常に狭くなります。従って観測者がスリットを通して太陽を見るのは非常に難しくなります。そのような条件のライン上に春分と秋分の太陽が入るのです。太陽は曲線を描いて沈んでいきますから、スリットと太陽の沈む曲線が交わったピンポイントの条件を満たして初めて起る現象です。それが、さらに春分と秋分の日という特別な日に起るのです。これは、三つ石が計算されて造られたことを意味しています。
『岩石遺構と太陽の関係の分類(平津豊、J-AASJ、2022-1 vol.4、2023)』では、スリットB-3型に分類されます。
また、この三つ石ではスリットによって定められるライン上にオレンジの線が入った石が据えられているので、この石を観測者が立つ補助点とするB-1型と捉えることもできますが、この石に立つとスリットを通して太陽を直視することはできないため、やはりB-3型に分類すべきだと考えます。
『イワクラ学初級編(平津豊、ともはつよし社、2016)』より
#イワクラ #磐座 #巨石 #megalith #古代祭祀 #巨石文明 #古代文明 #愛媛県 #松山市 #白石の鼻 #三つ石 #白石の鼻巨石群

本ページのリンクおよびシェアは自由です。
最近、本ページの内容をそのままコピーして転載しているサイトを見かけますが、本ページの内容、テキスト、画像等の無断転載(複製して他の媒体に公開)を固く禁じます。特に、まとめサイト等への使用を厳禁いたします。また、出典を明記しての引用は許可していますが、以下の引用のルールに則って行ってください。それ以外は「盗用」「剽窃」となります。1.引用元が明示されていること/2.引用部分が明確に区別されていること/3.引用部分を修正していないこと/4.引用する必然性があること/5.分量的にも内容的にも、自分の著作部分が主で、引用部分が従であること

[さらに詳細な情報]